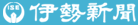伊勢新聞社は県民の皆様のおかげをもちまして、本年百二十年を迎えました。厚く御礼申し上げます。一口に百二十年ともうしますが、百二十年続く業種はきわめて希であるといわれています。しかも新聞社は事業の性質上もあって、取材、原稿書き、整理、編集、製版、印刷、配送まですべて社内にて自前で行う珍しい組織です。こんな業態はほかには無いともいわれています。
なぜこんな事業が長続きしてきたか考えてみますと、紙とインクの新聞のスタイルはあまり変わらないものの、制作する側の技術的変化はめざましいものがあります。コンピューターの進歩とともに、画期的変化を遂げてきました。常に外側から最先端のテクノロジーを導入し続けてきたのが伊勢新聞社であったということができると思います。
ワープロで作成した原稿を電話回線を通じて送る若手記者に伝書鳩を新聞社が飼っていたことを話しても冗談としか取られません。しかし一九七〇年頃まで大手新聞社でもハトを大量に飼育していたのです。もちろんファックスなどはほとんど存在していなかったのです。
新聞社の社員の職種に「ハト係」というものがあった、ということが伝説になっていくのもそう遠いことではないようです。(写真を送信する技術が確立しなくて、伝書鳩のお世話になっていたのです。年配の方は、災害現場からの第一報や写真がハトを通じてもたらされたことをご記憶だと思います)同様に、新聞社の整理部の職種に、「入力係」という技能職があったことも、笑い話になることは近いようです。(入力係とは、ファックスで送られてきた記者の原稿を、コンピューターに打ち込む仕事です。)
現在、日本新聞協会に加盟している日刊新聞社で、記者が原稿用紙を用いている社はありません。地方面の充実という点で申し上げれば、一九六〇年代交換留学生で渡米した高校生や大学生が、異口同音に驚きを込めて語った帰国談があります。「現地の学校に登校した日に地元の新聞社が取材に来て、翌日の新聞に掲載された。」という類のものです。残念ながら、当時の日本の新聞社の実力ではカバーできなかったようです。
現在、全国版、地方紙を問わず日本の新聞にも、海外からの留学生、語学補助要員のニュースは連日のように掲載されるようになりました。次に来るべきニュースは、結婚と死亡記事だといわれています。
こうした身近なローカル記事を、早く、大量に採り上げ続けて、紙面化して行けるのはデジタル技術のおかげであります。新聞社には撮影してきたフィルムを現像・焼き付けする暗室が必ず存在します。しかし、デジタルカメラの普及は暗室もかつての新聞社のハト小屋化する可能性を示しています。
小生が社長に就任してから、まる三年が過ぎました。この三十六ヶ月の間に、弊社の報道部・整理部等を除いた間接部門である総務・経理といった部署でさえ、新たに導入されたコンピューターは十一台を数えます。デスクトップパソコン・ノートパソコンからNTTより納入されたインタージェットと呼ばれるユニックスマシーンまで多種にわたっています。その間社員の数は微減という状態です。
松本清張の原作を映画化した「砂の器」のクライマックスで、村を追われた父子がお遍路さんの装束で四季の日本を巡るシーンがあります。「交通技術の発達で旅の形は変わったが、親と子の宿命は永遠に変わらない」という字幕がエンディングに掲げられていた記憶があります。新聞制作の技術はこれからも止まることなく進歩し続けますが、記者が人に取材するというスタイルは変わりません。
高度なテクノロジーも百二十年前と同じ、泥臭い方法が無くては、無用の長物でしかありません。一方、県民の情報開示への要求は高まるばかりです。この流れは明治十一年の自由民権運動以来とまるところがありません。ご協力をお願いして、明日よりの地方面刷新とインターネット・ホームページの増設のご挨拶とさせていただきます。