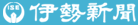「なんや、今日は休日か」。父が大声で叫んだ。
「運転手さんが出てこないはずだ」「一日得した」「千三、免許を取ったんだろう。今日はちょっと運転手をさせてやる」「いい天気だ。峠の茶屋でうまい飯を食わせてやるからな」と、甘い声を出されたらすぐ騙されるのが親子のDNAによるものだとは、当時の遺伝子学者も知らなかったであろう。
52年前、真夏の悪夢のような未熟運転者による迷路クルーズが始まった。起点は三重県四日市市諏訪町、行き先は告げられぬまま「俺の言う通りに運転しろ」という。暗闇運転というか、霧雨の中のドライブのごとき、快晴下の運転だった。
国道一号線を京都方面に向かった車は、「おきん茶屋」と呼ばれているらしい交通の要にあたる交差点沿いの大層古い木造の小さな食堂で、昼食を摂った。廃屋かとも思える店だが、年老いた女将が愛想よくもてなしてくれた。
失礼ながら「蜘蛛の巣城」のイメージが彷彿とする古い茶店であった。というのは、「小林社長さん、しばらくでした。お見限りでなく、寄っていただいて嬉しいですわ」と、白髪の老婆がお世辞を語り、父が「街道一の別嬪さんに会わずに通れませんよ」とのやり取りを聞いていると、冷房とてなく、扇風機もない古い店で、汗だくで、みそ汁と漬物でどんぶり飯をかっ込んでいる自分は、白昼夢の中の運転手の心地だった。
「そこを右に曲がれ。行き過ぎた、戻れ、下手くそ」「もっと早く指示してくれよ」と、親子喧嘩の口バトルが始まるのは当然の成り行きである。当時のクラウンのエアコンは、クーラーと称するのもおこがましい、扱い難いものであった。おまけにマニュアルシフトであった。どんどん山道に侵入して行って、峠のカーブを登りながら曲がると時折、車体の腹を擦るようになってきた。
「よし、ここで車を止めよ。降りて歩くぞ」と父は宣言した。「こんな山道で幅も狭いのに、車を止めて大丈夫なの?」「大丈夫だ、行き来する車なんてない」。石ころだらけの山道を歩きだしたが、帽子すら用意してない私は、ポロシャツもズボンも汗まみれになった。30分歩いただろうか、セミの鳴く音しか聞こえないまま、歩き続けた私は我慢の臨界点を超えて爆発した。
「お父さん、どこまで行くの、水が飲みたい。休憩所はないの?どこまで登っていくの?帰りはどうするの?」「やかましい、黙って歩け」と、父は激怒したのは予想通りだったが、常になく狼狽した様子を見せたのが不可思議だった。「しまった、逃げられた」と叫びながら、山道のわきの灌木に入っていくと小道があって、樹木の陰にひっそりと家が建っていた。「お前が大きな声を出すから気づかれた。馬鹿者」と罵られたが、何のことかさっぱり判らなかった。
「あそこを見よ」。指さす遠くの山腹に、こちらを振り返りもせずに懸命に駆け上がっていく男を目撃した。「〇〇さんはお出かけになりましたか、鈴鹿の小林が会いに来たとお伝えください」「もう戦争は終わったからいいじゃないですか」と、家から出てきた細君らしき女性が答えた。「いいや、終わってない。私は戦友たちのためにもお話ししたい。あの世で報告せねばならない、また来ます」。
「お前が騒ぐから、音を聞きつけられた」とだけ言って、父は自宅まで黙り込んだままだった。自宅に帰った私は、日に焼け疲れ果てて眠った。真夜中に目が覚めたが、どこからどこまでが夢なのか混乱していた。無性にのどが渇いて台所に行ったら、姉が水を汲んでくれて笑みを浮かべて語った。
「貴方も運転させられたのね。私も去年行ったよ。訪ねたあの人は元刑事よ。現役の時、占領軍の命令で戦犯狩りを熱心にしていたのよ。捕まえると特別報酬も出たらしいから、同じ日本人同士で戦犯逮捕の番犬と獲物に分かれたらしいわ。サンフランシスコ講和条約が結ばれて、戦犯無罪になってから攻守が変わって、刑事さんたちが軍人さんたちに追っかけまわされるようになったから、戦友のきずなは強くて、どこへ引っ越しても連絡網で追いかけてくるみたいよ、三重県にいる限りは。33連隊と55連隊でしょ」。夜中なのに、アブラゼミの鳴き声は止まらなかった。