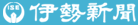医師や看護師が同乗して患者を救急搬送する「ドクターヘリ」の運航が三重県内で始まってから来年2月で10周年を迎える。新型コロナウイルス感染症の影響で出動件数は減少しているものの、医師や病院が不足する地域での救命活動には欠かせない存在となっている。この10年間でヘリの臨時離着陸場(ランデブーポイント)が増加し、出動を要請する救急隊員の能力も向上した。
基地病院の三重大医学部付属病院(津市)の一角には、ドクターヘリの運航を調整する部屋がある。消防本部から電話で出動要請を受けると、医師と看護師、パイロット、整備士の4人が機体に乗り込む。その間、約4分。行き先の詳細は飛び立った後で決まる。
ドクターヘリは同病院と伊勢赤十字病院(伊勢市)を基地病院として、平成24年2月に始まった。2病院が2カ月交代で運航。昨年度はコロナ禍で出動件数が238件にとどまったが、前年度までは年間300―400件ほどで推移してきた。
県内各地におおむね35分以内に到着することのできるドクターヘリは、複雑な地形や医療偏在に阻まれている地域の救命活動に貢献している。特に離島が多い県南部や、医師が不足している東紀州、伊賀地域で選択肢の1つとなっている。
ドクターヘリの出動要請が多い志摩市では、市内の県立志摩病院に救命救急センターがなく、伊勢赤十字病院まで陸路で1時間以上かかる。同市消防本部消防総務課の担当者は「住民は病院事情からヘリ搬送は有効と実感しているのではないか」と話す。
住民へのドクターヘリの浸透や県内各消防本部の積極的な活動により、救急車とヘリが合流するランデブーポイントの登録地点が徐々に増加。平成24年10月時点では県内で580カ所だったが、今月2日時点では643カ所にまで広がっている。
ただ、最初から円滑に運航できたわけではない。当初はどのような場面でドクターヘリを要請すべきかというノウハウがなかった。県内各消防本部の隊員や医師らが月に1回事後検証会を開き、出動を要請した事案を報告することで徐々にすり合わせていった。
志摩市消防総務課の担当者は「導入初期には要請をちゅうちょしてしまうこともあったが、毎月の検証会で改善された」と説明。加えて「この10年間で救急隊員の観察力が向上し、現場でドクターヘリの要請を判断するまでの時間が短くなっている」という。
県によると、ドクターヘリの運航には令和2年度で約3億6千万円かかり、このうち約2億5千万円を県と国が補助している。出動件数が少なかった2年度は1回当たりの出動に約150万円、平年並みの出動件数でも90―120万円かかっていることになる。
このコスト面について、ドクターヘリの導入段階から関わってきた三重大救命救急・総合集中治療センターの今井寛センター長は、県内の医療偏在を指摘した上で「地方に病院を建てるよりはヘリコプターで患者を運んだほうがいい」とみている。
一方で、課題もある。ドクターヘリは夜間、飛行できず、冬季は日没まで。天候が悪い日は飛ばせない。隣県の奈良、和歌山両県からヘリを飛ばすこともあるが、県内には1台しかないため、複数の消防本部が出動を要請した場合、優先順位を判断する必要がある。
人材の確保も急務だ。厚労省によると、県の人口10万人当たりの医師数は平成30年末で全国平均と比べて23・3人少ない223・4人。救急科は1・7人で、全国で43位となっている。今井センター長は「総合的に判断できる医師が必要」と語る。
県はドクターヘリの運航開始から10周年を迎えるのに合わせ、年明けの1―3月に県内の地域庁舎や基地病院を巡回し、パネル展を開催する予定。県医療政策課の担当者は「コロナ禍のため大規模なイベントを実施できないが、パネル展を通じて県民にドクターヘリへの理解を深めてもらいたい」。