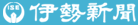昭和20年8月15日の終戦後、15歳で軍属見習い工として働いていた満州ハルピン郊外からシベリアへ連行された。ハバロフスクからシベリア鉄道で西へ約200キロのイズベストコーワヤの捕虜収容所、さらに北のツンドラ地帯にある2収容所で約2年の抑留生活を送った。
稲垣貞治さん(93)は、4年前に津市で開催したシベリア抑留関係展示会を観覧した折に住所氏名を記しており、全国強制抑留者協会三重県支部から届いた案内で4月の総会に参加し、抑留体験者であることが分かった。杉谷哲也副支部長は「私どもが知る限り、体験者の中で最年少ではないかと思う」と話している。
一志郡小野江村(現・松阪市肥留町)で6人きょうだいの次男として生まれた。昭和20年、国民学校高等科卒業と同時に14歳で軍属として満州に渡った。すぐに終戦となり、ソ連兵に武装解除を命じられ数百人とともに窓もない貨車に乗せられた。10日以上移動して降り立ったのはイズベストコーワヤの収容所だった。
収容所では身体検査があり、体が大きく丈夫そうな仲間は鉄道や道路工事などの重労働に、稲垣さんは小柄で150センチに満たなかったことで収容所内の雑役担当になった。しかし、毎朝の水くみ作業は過酷だった。数十センチの氷を割って2個のたるに川の水を入れ、てんびんで担ぎ収容所までの約2キロの悪路を往復する。途中、雪に足を取られ何度も転び、その度に水をくみに戻った。
鉄道の枕木を2人で運ぶ時は、相手と身長差があるので荷重がかかり、悲鳴を上げそうになるのを歯を食いしばって耐えた。朝食はサバ缶と渋皮のついたコーリャンのパン1切れ、昼と夜は煮た大豆をカップ1杯だった。氷点下40度の極寒と重労働の日々、栄養失調で仲間がバタバタと倒れていった。
風呂も入れず、ノミやシラミ、ダニで体中がかゆく眠れない。夜空に輝く北斗七星を見上げながら、懐かしい故郷を思い出して何度も涙した。こんな所で死んでたまるかと、生きて親兄弟に再会することを自身に誓った。連行されてから2年後、ナホトカ港から復員船「永緑丸」に乗って舞鶴港に着いた時は、言葉にできないほどの思いがこみ上げた。
兄と従兄弟が江戸橋駅に出迎えてくれ、家で待っていた母と手を取って再会を喜び合った。久しぶりに戻った実家は空襲で焼け、建て替えられていた。後になって、息子の安否を聞きに行った母に、県職員は「ソ連は鉄のカーテンだから何も分からない」と答えたと聞いた。
「ソ連帰り」「赤じゃないか」と噂が立ち、なかなか仕事も見つからなかったが、恩師の世話で印刷会社に勤めた後、四日市市役所を経て市立図書館で定年を迎えた。25歳で結婚し、息子2人を育てた。4年前に妻を亡くし、今は1人暮らしだが、近くに住む息子夫婦が時々寄ってくれるのがありがたい。
「ラーゲルの北斗七星凍て尽くす」。退職後は、俳句や書道に親しみ、シベリアでの抑留生活を思い出して多くの句を詠んだ。
「顔形、肌の色が違おうと皆兄弟。どれだけ相手に非があろうとも、戦争だけは絶対にしてはならない。ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルとイランの戦争など、今も悲惨な争いが続いているが、一刻も早く平和に解決してほしいと願っている」と話す。「戦争を知らない若い世代には、人ごとではない、世界情勢に無関心であってはならないと伝えたい」と力を込めた。