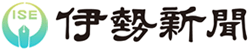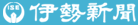【津】伊勢新聞政経懇話会の4月例会は23日、三重県津市新町のプラザ洞津で開いた。文筆家・皇學館大学非常勤講師の千種清美氏が「神宮式年遷宮にみる持続可能とは」と題して講演し、「変わることが継続につながる」と式年遷宮の意義と歴史を語った。
千種氏は「式年遷宮で皆さん疑問に思うのは何で20年に一度なんだろう、何で遷宮するんだろうということ」と述べ、①社殿尊厳説②世代技術伝承説③朔旦(さくたん)冬至説などを挙げ、「社殿はヒノキ新材、かやぶき、地面に直接立てる掘っ立て柱なので傷みますよね」「朔旦冬至は旧暦1月1日と冬至が19年ごとに重なる。月と太陽が暦で重なり、非常にめでたい」と説明した。出席者に賛成する説への挙手を求めたところ、「①②が多く、何人か③ですね。理由は文献に残されていない。分からないというのが正解。本当にどれなんでしょうね」と話した。
遷宮の理由は「神道では新しいものが持つ清浄性を尊ぶ。キーワードは常若(とこわか)」と述べた。
持統天皇が即位した690年に内宮の遷宮が始まり、692年に外宮が続いた。694年に藤原京へ遷都しているため、「天皇の代がわりごとに宮(皇居)遷(うつ)りをしていたのが、恒久的な都として藤原京へ遷都した。宮遷りが式年遷宮として継承されたと時代背景的には考えられる」とも指摘した。
戦国時代の遷宮中断後、「最初にお金を出してくれたのが織田信長。それを基に遷宮がぐっと進む。討たれて豊臣秀吉の時に復興し、内宮と外宮の遷宮がここから同じ年になる」と解説した。
式年遷宮の歴史を振り返り、「持続可能なポイントは変わること。変わらないものは継続できない」と強調。「長野県で6月に執り行う御杣始祭(みそまはじめさい)のご神木は、昔は木曽川水路。今は陸送でトラック輸送。桑名総社に入り、内宮と外宮に分かれ、外宮のご神木は津市の三重県護国神社に1泊する。ぜひお迎えください」と呼びかけた。
千種氏は地域誌「伊勢志摩」編集長を経て文筆家。平成25年の第62回式年遷宮の遷御の儀では式年遷宮広報本部のインターネット動画配信の司会進行を担当。県観光審議会委員、県文化振興計画評価推進会議座長を務める。最新刊は「伊勢神宮 式年遷宮参拝ガイド」(税別1600円、ワニブックス)。