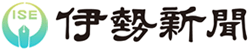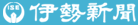三重県議会は11日、総務地域連携交通、環境生活農林水産、医療保健子ども福祉病院の常任委員会を開いた。地域連携・交通部は、県内の進捗(しんちょく)率が「全国46位」とされる地籍調査について、市町に実施したアンケートの結果を報告。地籍調査を担当する職員が平均で1・7人にとどまっていることを明らかにした。年間予算の平均も1858万円で、調査可能な面積は0・2平方キロメートル程度。県は進捗の引き上げに向けた「取組方針」を策定し、市町の調査を支援する方針。
地籍調査、専任職員配置はわずか8市町
<総務地域連携交通=野村保夫委員長、8人>
アンケート結果によると、地籍調査だけを担当する職員を置いているのは8市町にとどまった。他の21市町は専任の職員を置かず、他の業務と兼務させるなどして対応しているという。
地籍調査を休止している3市町を含め、14市町の年間予算が1千万円を下回っていることもアンケートで判明。20市町が地籍調査の実施計画を策定していないことも分かった。
県内の進捗(しんちょく)率(令和5年度末時点)は10%で、全国平均の53%を大幅に下回っている。県は昨年7月に県幹部でつくる検討会を設置し、地籍調査のペースを上げる方策を検討している。
県は地籍調査について「能登半島地震により、防災対策としての重要性が改めて認識された。進捗率の向上に加え、優先度を付けるなどして計画的に進める必要がある」としている。
「第2期ひきこもり支援推進計画」で最終案
<医療保健子ども福祉病院=石田成生委員長、8人>
子ども・福祉部は、来年度からの5年を対象期間とする「第2期ひきこもり支援推進計画」の最終案を示した。ひきこもりの当事者を対象とした居場所の数などを、数値目標として掲げた。
県によると、新たな計画は第一期の計画が本年度末で終了することなどを受けて策定。当事者や家族への支援、相談支援体制の充実、情報発信、社会参加支援などの7本柱で構成する。
計画では、ひきこもりの経験者らが相談に応じる窓口を、来年度中に設置すると明記。現状では45カ所とされる当事者の居場所を、令和11年度には60カ所に増やすことも掲げた。
計画には、ひきこもりの当事者や家族ら100人に実施したアンケート調査の結果も掲載した。当事者の六割が「支援があることを知らなかった」と回答したといい、県は支援機関の周知にも注力する方針。
豊かな海づくり大会向け、5月にリハ大会
<環境生活農林水産=廣耕太郎委員長、8人>
農林水産部は11月の「第44回全国豊かな海づくり大会」に向けた機運醸成のイベントを、5月31日に宿田曽漁港(南伊勢町)で開くと報告した。大会のリハーサルも兼ねて開く。
県によると、大会の開催前に開く大規模なイベントとしては、今回が唯一となる。当日はマダイの稚魚を放流するリハーサルや漁船のパレード、地場産品の販売などを予定している。
また、今月26日に開く県実行委員会の総会で、大会の実施計画を示す予定も報告。計画には式典や行事の具体的な内容に加え、来場者の輸送や宿泊の手配といった運営の方針も盛り込む。
この計画に基づいて大会の準備や当日の運営に当たる「大会実施本部」を4月中に立ち上げることも報告した。本部は県や志摩市、南伊勢町、関係団体などの職員で構成する予定。