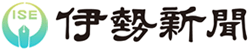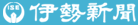【津】伊勢新聞政経懇話会の2月例会は20日、三重県津市新町のプラザ洞津で開いた。デンソーウェーブエッジプロダクト事業部主席技師の原昌宏氏が「社会を変えたQRコードの原点と成長」と題して講演した。
原氏はクイックレスポンスの頭文字を取ったQRコードについて「縦横二次元的に情報を持つ。特殊シンボルを3頂点に配置し、コードを見つける」と説明。特殊シンボルは「電車に乗っていて、あるビルの最上階にオーナーが住んでいたんでしょうね、窓が大きく印象に残っていた。それでコードに目印を付けることを考えた。バーコードと同等の読み取り速度を実現でき、非常に良かった」と振り返った。
「情報化時代に先駆けて開発した」として、鉄道会社での磁気切符の廃止やホームドアの制御、ホテルのチェックインなどQRコードの普及と進化を紹介。店舗情報があるQRコードを床全面に張り巡らしたショッピングモールや、建物や布団の全体にQRコードをデザインしたホテル、ドローンを飛ばしてQRコードをつくるイベントなど海外の事例も挙げ、「クリエイティブな使い方。日本には遊び心がない」と話した。
日本の現状に対し「情報時代に乗り遅れた。特にビッグデータの活用ができていない」「ビッグデータをAI(人工知能)で解析し、人の行動や要望、消費動向、商品の生産、流通状況の可視化が、QRを使ってできるだろう」と展望した。
また「単純なアイデア程度のものでも世の中が変わればイノベーションになる。新規開発には見切り発進が必要。行動してみて初めて分かることが多くある。失敗から学び取る力が、成功する一番の近道になる」と呼びかけた。
原氏は昭和55年、日本電装(現デンソー)に入社し、新規事業の製品開発に従事した。最初にコンビニのレジで使用しているバーコードスキャナ、次にOCR(印刷された文字をコンピューターが利用できるテキストデータに変換する技術)を開発・製品化し、情報読み取り装置の開発経験から平成6年にQRコードを生み出した。現在はQRコードの進化と新たな用途開発に取り組んでいる。昨年から福井大学客員教授、名古屋学院大学特任教授を兼務している。