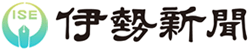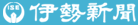埼玉県八潮市の道路陥没をきっかけに、公共インフラの老朽化が懸念されている。三重県の橋や道路も多くは高度経済成長期に完成し、老朽化は深刻な状況。その維持管理費は県財政に重くのしかかる。
県によると、県が管理している4216の橋のうち、建設から50年以上が経過したものは令和3年時点で44・2%だった。一方、13年には63%、23には79%と、急増する見通しとなっている。
公共インフラの維持管理費は増加の一途をたどる。県は来年度一般会計当初予算で、国の補助がない「県単維持事業」の費用に181億5千万円を計上。傷んだ道路の修繕や河川の堆積土砂撤去などに充てる。
県単維持事業は増加の一途をたどる。8年連続で増加し、5年連続で過去最多を更新。平成27年度(89億円)の約2倍に当たる。資材価格や労務費の上昇、インフラの増加などが増加の主な理由という。
かさむ維持管理費に、どう対応しているのか。県はそれぞれのインフラに「長寿命化修繕計画」を策定。早期に異常を把握して対処する「予防保全」を実施することで、将来的に必要な維持管理費の軽減を図っている。
一方で「予防保全をしても、毎年度の維持管理費が今より減ることはないだろう」と、県土整備部の担当者。過去最大規模となった来年度の維持管理費も「必要な分は確保できたが、十分とは言えない」と話す。
新たな道路の整備などに比べ、維持管理費は国からの補助が出にくいという事情もあるようだ。県は毎年度、道路舗装の修繕に数10億円を要望しているが、実際に支援が決まるのは、その数%とされる。
さらには、維持管理の「移管」による負担増も懸念される。国が国道のバイパスを整備した場合は、既存の国道の維持管理を都道府県に移管するのが原則。「大きな国道の管理が県に移管されれば、現状の予算では追いつかない」(県担当者)という。
学校関係の施設の老朽化も懸念される。県立亀山高では先月、校内の電柱2本(高さ約6メートル)が折れる被害があった。これまでの定期点検で異常はなかったが、電柱は製造から約50年が経過していた。
「インフラの維持管理は県民生活に直結する重要な業務。安全性や緊急性などを加味して対応したい」と、県の担当者。人口減少時代に限りある予算と人材をいかに投入するか。的確な優先度判断が求められる。