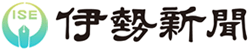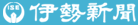【四日市】四日市市曽井町の神前小学校の3年生49人が6日、社会の授業の一環で、学校前にある神前郷土資料館(同市高角町)を訪れ、主に昭和期に使われていた農具や生活用具などに触れ、当時の暮らしぶりを学んだ。
神前風物詩編集委員会のメンバーら3人が案内役を務め、展示品の説明をした。館内は「農業」「養蚕」「生活用品」に分けて展示がされ、農業のコーナーでは、玄米を品質の良い米、小米、もみに分ける大正時代の米選機の使い方を教わったり、足踏み式の脱穀機のペダルを踏んで回転させてみたり。
生活用品のコーナーは、たらいや火鉢などが並び、五右衛門風呂の中に入った中村翼さん(9つ)は「すごく深い!」と驚いていた。
児童らは熱心に質問し、聞いたことを紙にびっしりと書いていた。この日、学んだことや興味を示したことをさらに詳しく調べて後日、国語の授業で発表する予定という。