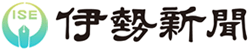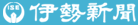▼東京支社に赴任して2年余で本社に戻った同僚が生活習慣の変化について社内報に書いていた。特に歩く距離の違い。電車を乗り継ぎ支社に通った日々は一日1万歩近く歩いていたが、車に依存する今は2千歩がやっと。地方暮らしより都会の方が健康的にはいいのではないかと言っていた
▼本紙『ウェルビーイングの条件』で千葉大予防医学センターの近藤克則特任教授も必要に迫られる都会の方が歩行量は多くなると書いている。一方、歩きやすい街づくりの必要性も説いている。歩くのに適した歩道や公園近くに住む人は膝痛が15%、腰痛が6%少なく、高齢者7万6千人を3年間追跡調査した結果、歩道面積割合が多い地域に暮らす人は、うつが少なく、認知症発症リスクも45%低かったという
▼生鮮食料品店が近くにあることで介護費用の大幅節約になるとも言い、どんな環境に住むかで健康寿命は変わる。県でひところ官民あげてウオーキングやジョギングが奨励されたが、すっかり冷え切ってしまったようにみえる。平成19年、伊勢市長が「健康文化都市宣言」を提唱し、内臓脂肪症候群の疑いのある職員7人を「メタボ侍」として先頭に掲げて減量作戦を展開したが、7のうち1人が運動中に急死した
▼8月中旬で、当時は運動中止も今ほど強い要請ではなかったろう。整備された歩道に緑豊かで美しい街並み、レクリエーション施設や公園、公共施設に商店街など、気持ちよく歩ける環境づくりを近藤教授は薦める。福祉と医療、地域振興が一体となった街づくりだ。