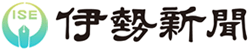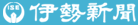国の文化審議会が3月15日、松阪市の宝塚古墳から出土した国内最大級の船形埴輪(はにわ)などの国宝指定を答申し、8月27日に国宝「宝塚1号墳出土埴輪」として指定された。国宝は歴史・学術上の価値に加え美術性も求められ、素焼き土器の埴輪はこれまで2件だった。文化庁は船形埴輪について「全体の9割ほどが遺存する希有な例であり、造形性、装飾性にも優れる」と評価する。
指定対象の埴輪は船形、囲形、家形の他、埴輪残欠や土器・土製品を含め計278点に上る。国宝は同市初で、県内では7件目となる。
宝塚1号墳(同市宝塚町・光町)は5世紀初めに造られた前方後円墳。伊勢国最大の全長111メートルを測る。平成11年度から3年間、史跡整備のため発掘調査し、船形埴輪などが見つかった。
埴輪を所有する同市文化財センターは情報誌「はにわ通信」4月号で国宝決定を喜び、国宝埴輪の「すごいところ!」として「設置されたままの状態で出土」「船形埴輪は全長140センチ、幅36センチ、台座を含め高さ94センチで国内最大級の大きさ。大刀(たち)、威杖、蓋(きぬがさ)が備えられ全国唯一」とアピールする。
さらに「船形埴輪全体はベンガラ(酸化鉄で作る濃い赤の塗料)で塗られていて、一部は今も残っています」と紹介する。当初は赤い船だった。
「万葉集」巻16に異界を渡る赤い船を詠んだ歌「沖つ国(海の果ての他界で、死霊の赴く地) うしはく君(支配者)の 塗り屋形 丹塗りの屋形(魔よけに赤く彩色した屋形船) 神の門(と)渡る」(三八八八番)がある。宝塚古墳に眠る支配者と赤い船の埴輪が、歌の世界と一致する。
江戸時代に見つかった国宝の「漢委奴(かんのわのな)国王」金印(福岡市)も、後漢の光武帝が57年に倭の奴国に印綬を下賜したという「後漢書」の記述を裏付け、考古資料と文献が合致した。
同歌は「怕(おそろ)しき物の歌(畏怖の対象となる霊(もの)を題材とする歌)」三首の一つ。次の三八八九番は「人魂の さ青なる君が ただひとり 逢へりし雨夜(人魂そっくりの青白い顔をしたあのお方が、たった一人、ふわりと現れた、あの暗い雨の夜)」というぞっとする内容。
「新潮日本古典集成 萬葉集四」によると、巻16は歌集全体の付録の位置付けで「愉快な歌ばかりが集まっている。寝転ぶようにして最も気楽に読める」とされ、前掲歌は「諸地方の民謡・芸謡」から取り入れた。古代人の死生観を反映している。
国宝決定後に刊行された和田晴吾立命館大学名誉教授の「古墳と埴輪」(岩波新書)に宝塚古墳の船形埴輪が取り上げられている。「古墳からは船を描いたものや、船の形を象(かたど)ったものが少なからず出土し、時には船そのものも見つかっている」と指摘し、「他界へと死者の魂を乗せて行った船」とされる。
同市文化財センターは国宝決定記念の企画展「深掘り!宝塚1号墳の埴輪」や特別展「王権と首長墓の埴輪」を開催。「大切な宝(文化財)を保存・公開し、未来につなげていくためにチーム一丸となって頑張ります」と意気込む。頑張りに期待したい。