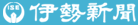▼桜の花びらが1枚、目の前をよぎっていく。昨夜の雨と風ですっかり散ったと思ったが、小さな並木道を歩くとわずかに残り、幹から出た小枝にしっかりした花がしがみつくように三つ四つ。ウグイスがケキョケキョと、懸命に鳴き方を練習している
▼8日は花まつり。代名詞の「花」はほとんどあるまい。「月にむらぐも花に風」は古来からの言い回しだが、不安定なこの時季の季節を言い当て、井伏鱒二も「花に嵐のたとえもあるぞ」として言っている
▼春雷、春嵐、花冷えなど、日本人は2月4日を「立春」と名付けて早々と春の息吹きを見いだそうとしてきたが、春の盛りになると、その一挙手一投足、自然の移ろいに神経を注ぎ、去るを恐れる
▼「花」はかつては梅を指し、万葉集には118首採歌されてハギに次いで2位。桜は5位で40首。平安宮内裏の紫宸殿の「左近の桜・右近の橘」も、元は「左近の梅」だったといわれる。古今集では桜が筆頭で、梅は衰退。日本の風景として伝承されているのは「梅にウグイス」か
▼梅は冬を耐え抜く象徴で、桜は一気に開放された喜びとして日本人の好みとして取って代わっていったのかもしれない。吉田兼好が『徒然草』で「花は盛りに、月はくまなきをのみ見るものかは」と言っているのも、いわば屈折した愛情か
▼桜の怪しい雰囲気を作品にしたのが坂口安吾の『桜の森の満開の下』で、今昔物語からの構想。清少納言は「桜など散りぬるも、なほ世の常なりや」。知人の出家に世の無常を感じ、散る桜に例えている。