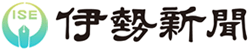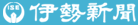約30年に及ぶ観測により、飛騨高山の森林生態系の炭素吸収に対する長期的・短期的な気候変動の影響を検出

岐阜大学
約30年に及ぶ観測により、飛騨高山の森林生態系の 炭素吸収に対する長期的・短期的な気候変動の影響を検出
産業技術総合研究所環境動態評価研究グループ、国立環境研究所地球システム領域、岐阜大学環境社会共生体研究センター(村岡裕由教授・センター長)による研究グループは、岐阜県高山市の標高1400mにある岐阜大学環境社会共生体研究センター高山試験地の落葉広葉樹林における約30年に及ぶ長期観測によって、森林生態系の二酸化炭素吸収量の季節変化と年々変動を明らかにし、これらの要因として、長期的・短期的な気候変動と森林の成長がもたらす影響を分析しました。
本研究の成果は、地球温暖化が進行する現在から将来における森林の地球環境調節機能の診断や、気候変動の影響を予測する手法の精度向上など、持続可能な社会の構築に資する自然生態系に関する知見となります。
本研究は、2024年6月23日付けで、Wiley社から刊行されるアメリカ地球物理学連合の学術雑誌『Journal of Geophysical Research: Biogeosciences』に原著論文として掲載されました。
【研究背景】
森林は地球表面の約10%に分布しており、地球規模の炭素循環や水循環、生物多様性の維持において重要な役割を果たしていることが知られています。現在では人類が排出する二酸化炭素のうち約30%を森林などの陸上生態系が吸収すると算定されています。しかし、生態系における光合成による二酸化炭素の吸収量や呼吸による放出量、及び、これらの収支(炭素収支とも言われる。生態系による正味のCO2固定量のこと)は毎日、季節、年などの時間によって変動することは知られているものの、そのメカニズムや気候変動に対する応答(気候変動による影響)はよくわかっていません。時間的にも空間的にも変化が著しい自然環境の状態を調査し、そのメカニズムを解明するためには、長期間にわたる観測データが必要とされますが、こうした研究に有用な長期観測研究は世界的にも稀です。
【研究成果】
産業技術総合研究所と岐阜大学は、1993年に岐阜県高山市にある岐阜大学・流域環境研究センター(当時)・高山試験地周辺の冷温帯落葉広葉樹林において、大気と森林生態系の間の二酸化炭素の収支を観測するためのタワー(高さ27m)を建設し、以来、大気中のCO2濃度や気象の観測、さらに森林によるCO2の吸収速度の観測を続けています(図1)。現在ではアジア地域で最も長期間、世界的にも有数の長期間にわたる約30年分のデータが蓄積されています。本研究では、得られたデータから年間炭素収支の年々変動と長期傾向を解析し、それらの原因を明らかにするために気象や森林の環境要素との関係を調べました。
生態系の CO2 または炭素の収支(=生態系純生産量、 Net Ecosystem Production,NEP )は、光合成による吸収量(総一次生産量、 Gross Primary Production,GPP )と呼吸による放出量によって決まります。研究グループは観測タワーにおいて「渦相関法」 (1 と呼ばれる観測手法を用いて計測し続け、毎日 30 分間隔で炭素収支を算出しました(図2)。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202406262742-O8-qRUgNjp3】
図1 岐阜大学環境社会共生体研究センター高山試験地に設置されている観測タワー
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202406262742-O6-quJsZQL6】
図2 観測タワーにおいて計測された森林の炭素収支(=光合成量―呼吸量)、光合成量、呼吸量の年々変動。これらの項目は炭素フラックス(=流束)と呼ばれ、各項目の数値は1年間あたり、森林1㎡あたりの炭素重量で表される。
その結果、(1)1年間あたりのNEPは、森林の葉量や、光合成活動に影響を及ぼす気象条件の影響を受けて顕著な季節変化を示し、さらに年々変動すること、(2)NEPの年々変動は、呼吸による炭素放出量の年々変動よりも光合成による炭素吸収量(GPP)の年々変動の影響を大きく受けていること、(3)毎年のNEPやGPPは、夏季のNEPやGPPの大小に影響されて、これが年々変動に至っていること、(4)1年間のNEPやGPPは、森林樹木の展葉から落葉までの期間の長さの影響を受けていることが明らかになりました。また、夏季(当地では6月〜9月)のNEPやGPPの年々変動は、夏季の日射量や森林全体の葉量(葉面積指数)の影響を受けることも示されました。2004年の台風による撹乱が起きて森林の枝葉が落ちると森林の光合成量が低下しますが、その後数年から10年程度をかけて枝葉が成長すると、光合成量が増加します。
他方で、特に最近10年間(2013―2021年)では夏季の日射量の増加と大気の水蒸気飽和度(飽差)の増加がGPPの低下を生じている可能性が示唆されました(図3)。また、1年間のうち毎日の光合成量が呼吸量を上回る期間の年々変動は、春の気温と初秋の日射量の変動の影響を受けていました。すなわち、春の気温の上昇は正味の炭素吸収の開始時期を早め、初秋の日射量の増加は正味の炭素吸収の終了時期を遅らせるというメカニズムが示唆されました。春の気温と初秋の日射量との間の関係性にはエル・ニーニョ現象(2が関与していると考えられています。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202406262742-O9-fivWD0r1】
図3 観測タワー周辺で計測された森林の全葉面積(葉面積指数)。夏季にあたる6月から9月の毎月の計測値を示す。2004年に到来した台風により枝葉が落ち、その後、約10年かけて葉面積指数が回復したことがわかる。
【今後の展開】
本研究の結果、地球環境調節において重要な役割を担う森林生態系の炭素吸収機能は、光合成や呼吸などの生態学的なメカニズムの時間的変動、及び、長期・短期的な気候変動の影響を受けることが明らかとなりました。地球温暖化は今後もさらに進行することが予測されています。カーボンニュートラル推進や生物多様性保全、さらに私たちが自然から受ける恵み(生態系サービス)を持続可能なものとするためにも、自然生態系の状態を適切に診断するとともに、将来の自然生態系の姿と機能をより正確に予測することが必要とされます。このためには、高山試験地で継続されているような生態系と気候変動の観測研究、及び、関連する様々な地球環境研究を学内外、国内外の共同研究によって進められることが不可欠です。
岐阜大学環境社会共生体研究センターではさまざまな研究機関や大学等との共同研究を推進し、地球環境保全と地域の環境課題の解決策に貢献します。
【用語解説】
1) 渦相関法:
森林上空の大気中の二酸化炭素の流束を高頻度で測定し、森林が吸収または放出する炭素量を定量化する手法。
2) エル・ニーニョ現象:
赤道太平洋の海面水温が異常に上昇し、世界中の気候に大きな影響を与える気象現象。
【論文情報】
雑誌名:Journal of Geophysical Research: Biogeosciences
論文タイトル:Interannual variation and trend of carbon budget observed for more than two decades at Takayama in a cool-temperate deciduous forest in central Japan.
著者:Shohei Murayama、 Hiroaki Kondo、 Shigeyuki Ishidoya、 Takahisa Maeda、 Nobuko Saigusa、 Susumu Yamamoto、 Kazuki Kamezaki、 Hiroyuki Muraoka
DOI: 10.1029/2023JG007769
リリースURL:https://kyodonewsprwire.jp/release/202406262742
注意:本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。詳細は上記URLを参照下さい。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。